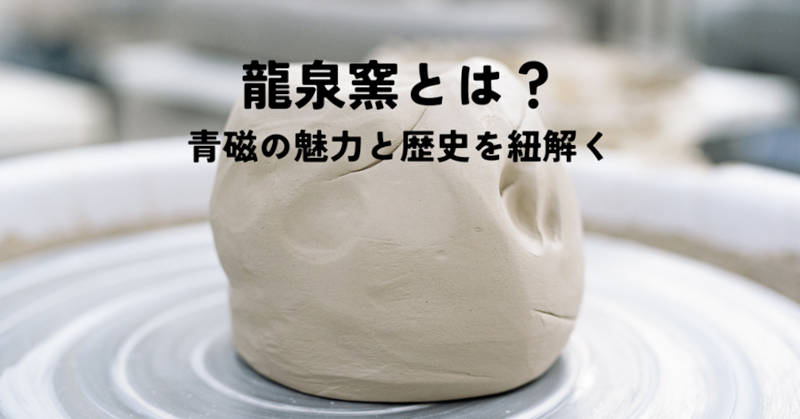
龍泉窯の青磁は、その独特の青緑色の釉薬と洗練されたフォルムで、古くから人々を魅了し続けてきました。中国浙江省龍泉県で生産されたこの青磁は、宋代から明代にかけて隆盛を極め、日本にも数多く輸入され、皇室や大名などによって珍重されました。
今回は、龍泉窯の歴史を簡潔にまとめつつ、その青磁の色調、釉薬、形状、装飾技法といった具体的な特徴を分かりやすく解説します。それぞれの時代の青磁を比較することで、龍泉窯青磁の魅力をより深く理解していただけるよう努めます。
【目次】
龍泉窯の歴史と概要
宋代からの発展
南宋~元時代の隆盛
明代以降の変遷
龍泉窯の特徴
色調と釉薬の種類
形状と大きさのバリエーション
装飾技法の解説
龍泉窯の特徴を比較して理解する
龍泉窯の特徴!他の青磁と比較する!
まとめ
骨董品の買取は永寿堂へおまかせ下さい!
龍泉窯の歴史と概要
宋代からの発展
龍泉窯は、中国浙江省龍泉県とその周辺地域で、唐代後期から青磁や黒釉の陶磁器の生産が始まりました。
しかし、本格的な青磁生産は北宋時代に入ってからのことで、特に南宋時代から元代にかけて最盛期を迎えました。
この時代には、海外への輸出も盛んになり、日本にも多くの青磁が伝来しました。
初期の龍泉窯の青磁は、淡い青緑色をしており、日用品を中心に生産されていました。
南宋~元時代の隆盛
南宋時代には、龍泉窯の技術はさらに高度化し、灰色がかった白い素地に淡い水色の釉薬をかけた、美しい青磁が作られるようになりました。
この時代の青磁は、日本では「砧青磁(きぬたせいじ)」と呼ばれ、高く評価されました。
砧青磁は、薄く繊細な胎土に厚く釉薬をかけたものが多く、澄んだ色調と穏やかな光沢が特徴です。
南宋官窯の青磁と比較すると、龍泉窯の青磁は、陽刻、陰刻、貼花といった精巧な装飾を施したものが多い点が異なります。
南宋官窯は陶器質の黒い胎土にガラス質の釉薬をかけ、貫入が多く見られるのに対し、龍泉窯の砧青磁は磁器質の白い胎土に、貫入の少ない澄んだ釉薬が特徴です。
元時代に入ると、西アジアやモンゴルからの需要増加に対応するため、大型の壺や花瓶などの生産が増加しました。
これらの青磁は、室町時代の貿易船「天龍寺船」で日本に伝来したことから、「天龍寺青磁(てんりゅうじせいじ)」と呼ばれています。
天龍寺青磁は、砧青磁と似た色合いですが、やや黄色みを帯びた釉薬が使われることが多く、大型で重量のある作品が目立ちます。
また、印花や貼花といった装飾技法も盛んになり、鉄絵具を上から垂らした「飛青磁(とびせいじ)」も作られました。
大型の作品は、首、胴、高台などのパーツを分けて制作されていたと考えられています。
明代以降の変遷
明代に入ると、青磁の流行は白磁や青花へと移り変わり、龍泉窯は徐々に衰退していきます。
しかし、明代にも優れた青磁は生産されており、明の七官という官位の人によって日本に持ち込まれたことから「七官青磁(しちかんせいじ)」と呼ばれています。
七官青磁は、灰色がかった濃い青緑色で、光沢が強く、細かい貫入が多く見られるのが特徴です。
釉薬の色調は、それまでの砧青磁や天龍寺青磁とは明らかに異なっており、より深い緑色を帯びています。
形状も多様化し、動物をモチーフにしたコミカルな香炉なども作られました。

龍泉窯の特徴
色調と釉薬の種類
龍泉窯青磁の色調は、時代によって変化しました。
初期は淡い青緑色でしたが、北宋時代には緑青色、南宋時代には明るい青色へと変化していきました。
明代になると、灰色がかった濃い青緑色になり、透明感と光沢が増し、細かい貫入が入るようになります。
釉薬の種類も、時代や作品によって微妙な違いがあり、それによって色調や光沢に変化が生じています。
釉薬の厚さや、焼成温度、窯の雰囲気など、様々な要因が複雑に絡み合って、龍泉窯青磁独特の色合いを作り出しています。
形状と大きさのバリエーション
龍泉窯では、皿や碗といった日用品から、大型の壺や花瓶、香炉など、様々な形状の青磁が作られました。
特に元時代以降は、大型化の傾向が顕著で、高さ30cmを超えるような大作も少なくありません。
形状のバリエーションも豊富で、シンプルなものから、複雑な装飾が施されたものまで、多様な作品が存在します。
それぞれの時代の流行や、用途、そして顧客の要望に応じて、形状や大きさが変化していったと考えられます。
装飾技法の解説
龍泉窯青磁の装飾技法には、陽刻、陰刻、貼花などがあります。
陽刻は、表面を盛り上げて模様を表現する技法で、陰刻は、表面を彫り込んで模様を表現する技法です。
貼花は、別の粘土で作った模様を貼り付けて焼く技法です。
これらの技法は、時代や作品によって使い分けられており、それぞれの技法によって異なる表現が可能です。
また、鉄絵具を使った装飾も施され、特に元代の天龍寺青磁では、鉄絵具を釉薬の上に垂らした「飛青磁」が多く見られます。
龍泉窯の特徴を比較して理解する
龍泉窯青磁は、時代によって色調、形状、装飾技法に違いが見られます。
砧青磁は、澄んだ青緑色で、薄く繊細な胎土に厚く釉薬をかけたものが多く、穏やかな光沢が特徴です。
天龍寺青磁は、やや黄色みを帯びた釉薬で、大型で重量のある作品が多く、印花や貼花などの装飾が施されています。
七官青磁は、灰色がかった濃い青緑色で、光沢が強く、細かい貫入が多く見られます。
これらの違いを比較することで、龍泉窯青磁の時代区分や特徴をより深く理解することができます。
それぞれの時代の青磁は、その時代の技術や美意識、そして社会情勢を反映した結果であると言えるでしょう。
龍泉窯の特徴!他の青磁と比較する!
龍泉窯青磁は、中国の他の窯で生産された青磁とは、色調、釉薬、胎土などに違いがあります。
例えば、南宋官窯の青磁は、龍泉窯の青磁と比べて、胎土が黒く、釉薬がガラス質で、貫入が多く見られます。
汝窯の青磁は、龍泉窯の青磁と比べて、より淡い青緑色で、上品な雰囲気を持っています。
景徳鎮窯の青白磁は、龍泉窯の青磁と比べて、青みが少なく、白に近い色調をしています。
これらの違いは、使用する粘土の種類、釉薬の成分、焼成方法など、様々な要因によって生じます。
龍泉窯青磁は、他の青磁と比較することで、その特徴がより明確になります。

まとめ
龍泉窯は、中国浙江省龍泉県で宋代から明代にかけて栄えた青磁窯です。
その青磁は、時代によって「砧青磁」「天龍寺青磁」「七官青磁」と分類され、それぞれ色調、形状、装飾技法に特徴があります。
砧青磁は澄んだ青緑色で繊細、天龍寺青磁は大ぶりで装飾豊か、七官青磁は濃い青緑色で貫入が多いのが特徴です。
日本にも多く輸入され、皇室や大名に珍重された龍泉窯青磁は、その歴史と技術の高さから、現在も高い評価を受けています。
本記事で紹介した特徴を参考に、龍泉窯青磁の魅力をより深く理解していただければ幸いです。
龍泉窯青磁は、時代を超えて人々を魅了する、優れた陶磁器と言えるでしょう。
その美しさは、単なる装飾品ではなく、歴史と文化を凝縮した芸術作品として、私たちに語りかけてきます。
投稿者プロフィール 永寿堂は、名古屋市を拠点に愛知・岐阜・三重を含む東海三県を中心に、全国を対象に骨董品買取を専門としております。お客様が大切にされてきた骨董品一つひとつに心を込めて査定し、適正な価格での買取を心がけています。当社は、骨董品の知識を有する専門家が直接お伺いし、適切な金額で買取査定を可能にします。 |
骨董品の買取は永寿堂へおまかせ下さい!
 骨董品の売却は骨董品買取店である永寿堂におまかせ下さい。名古屋市をはじめ愛知県や岐阜県や三重県などへ出張費無料にて買取りに伺います。気になる方は電話やメールへお問い合わせ下さい。
骨董品の売却は骨董品買取店である永寿堂におまかせ下さい。名古屋市をはじめ愛知県や岐阜県や三重県などへ出張費無料にて買取りに伺います。気になる方は電話やメールへお問い合わせ下さい。
骨董品買取専門店 永寿堂へのお問い合わせ先
・TEL:0120-060-510
・メール:info@eijyudou.com
・LINE ID:@721crjcp
骨董品コラムの
ピックアップ記事
2024.04.03
茶道具と骨董品の世界!歴史と美の交差点を探る
2024.01.25
高く売れる骨董品とは?価値が上がるジャンル・特徴・見極め方を徹底解説
2022.05.18
骨董品の種類まとめ|価値のあるものの特徴や高く売るためのポイントを解説
2024.04.26
価値ある骨董品とは?有名な骨董品作家についてご紹介!
2024.01.05
骨董品の買取相場はいくら?買取時のポイントや買取方法などを解説!
2024.03.30
なぜ骨董品の需要が高いの?需要の秘密と価値を高めるコツもご紹介!
2024.10.04
高い買取価格を期待できる銀瓶の特徴とは?買取業者を選ぶポイントも紹介
2023.01.07
書道具の買取相場は?高く売れる書道具の特徴や高く売る際のポイントも解説
2025.02.06
中国茶器とは?茶器の種類や中国茶のおいしい淹れ方などをご紹介
2022.05.23
茶道具の種類20選!道具としての使い方や高く売る3つのポイントを紹介
2024.08.20
鉄瓶の買取相場とは?高く売るための鉄瓶の種類と特徴













